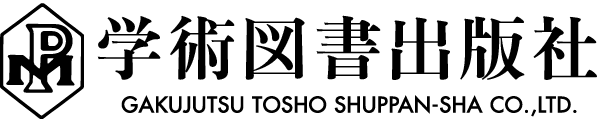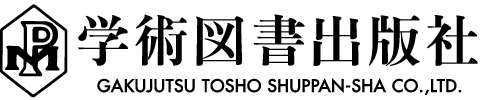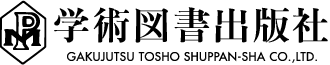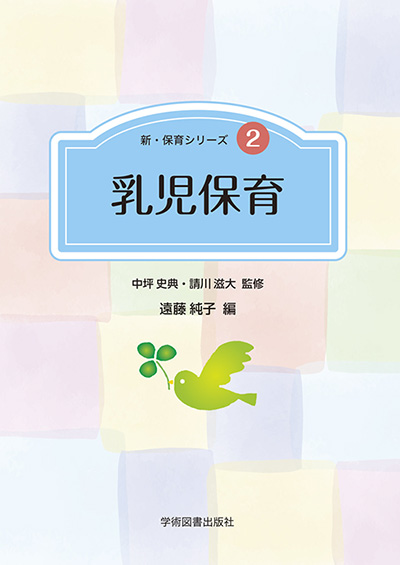
- 判 型
- B5
- ページ
- 210
- ISBN
- 978-4-7806-1389-6
- 発 行
- 2025年10月
定 価 2,200円(本体 2,000円)
第1章 乳児保育の意義
1.1 乳児保育をめぐる現状
1.2 乳児保育の質の確保・向上のために
1.3 これからの乳児保育が目指すもの
第2章 乳児保育の歴史
2.1 乳児保育の始まり(明治~昭和初期)
2.2 乳児保育の基盤づくり(戦後~1980年代)
2.3 乳児保育の普遍化(1990年代~現在)
第3章 乳児保育における養護及び教育
3.1 養護と教育の一体的展開とは
3.2 3つの視点と5つの領域
第4章 子育て家庭を取り巻く社会的状況と課題
4.1 子育て家庭の変化
4.2 子育て家庭を取り巻く社会的状況と課題
第5章 諸外国における乳児保育
5.1 韓国の乳児保育
5.2 フィンランドの保育
第6章 保育所・認定こども園における乳児保育
6.1 保育所・認定こども園における乳児保育の概要
6.2 保育所・認定こども園における乳児保育の実際
第7章 乳児院における養育
7.1 乳児院とは
7.2 乳児院における職員の役割
7.3 担当養育制について ─アタッチメントを基本に─
7.4 育ちをつなげるために
7.5 保護者・家族支援、里親支援について
7.6 地域支援 ─家族と一緒に暮らし続けられるために─
第8章 小規模保育・事業所内保育における乳児保育
8.1 地域型保育事業の概要
8.2 小規模保育事業
8.3 事業所内保育事業
第9章 家庭的保育・居宅訪問型保育における乳児保育
9.1 家庭的保育事業とは
9.2 家庭的保育(保育ママ)とは
9.3 居宅訪問型保育とは
9.4 家庭的保育・居宅訪問型保育の遊びや生活の環境
9.5 家庭的保育・居宅訪問型保育の良さと課題
第10章 乳児保育における計画・記録・評価
10.1 保育の計画とは
10.2 乳児保育における指導計画
10.3 乳児保育における記録・評価
第11章 職員間の連携・協働
11.1 保育者間の連携・協働
11.2 多職種での連携・協働
11.3 職員間の対話
第12章 入園・進級時の配慮
12.1 入園時の子どもの様子と保育者の配慮
12.2 進級時の子どもの様子と保育者の配慮
12.3 3歳以上児の保育に移行する時期の保育
第13章 保護者との連携・協働
13.1 近年の保護者・家族支援
第14章 自治体や地域の関係機関等との連携・協働
14.1 自治体における子育て支援の取り組み
14.2 子どもを安心して生み育てるために
第15章 子どもと保育者の関係の重要性
15.1 「養護」において大切な関係性
15.2 「教育」において大切な関係性
第16章 6か月未満児の育ちと保育①
16.1 6か月未満児の発達の概観と配慮事項
第17章 6か月未満児の育ちと保育②
17.1 6か月未満児の基本的生活習慣と援助
第18章 6か月以上1歳未満の育ちと保育①
18.1 身体の発達
18.2 心と言葉の発達
第19章 6か月以上1歳未満の育ちと保育②
19.1 生活の流れ
19.2 排せつと着脱
19.3 遊び
第20章 1歳以上2歳未満児の育ちと保育①
20.1 1歳以上2歳未満の発育・発達の特徴
第21章 1歳以上2歳未満児の育ちと保育②
21.1 1歳以上2歳未満児の生活と遊び
第22章 2歳以上3歳未満児の育ちと保育①
22.1 「やりたい」や「こだわり」を受け入れる
22.2 信頼関係づくりと自発性・探索意欲の高まり
第23章 2歳以上3歳未満児の育ちと保育②
23.1 1日の流れと保育の環境
23.2 低年齢児の生活と遊びにおける援助の実際
第24章 乳児保育と食
24.1 乳児保育における食の援助
24.2 食事における配慮点
24.3 スプーンの持ち方の変化、遊びとのつながり
第25章 配慮が必要な子どもの保育①
25.1 1人ひとりの育ちを理解する
25.2 特に配慮が必要な“気になる子”の支援
第26章 配慮が必要な子どもの保育②
26.1 疾患のある子ども
26.2 医療的ケアが必要な子ども
26.3 医療的な配慮が必要な子どもを受け入れる際の配慮
第27章 乳児保育と環境①
27.1 保育の環境とは
27.2 0歳児クラスの生活の環境
27.3 1歳児クラスの生活の環境
27.4 2歳児クラスの生活の環境
第28章 乳児保育と環境②
28.1 0歳児クラスの遊びの環境
28.2 1歳児クラスの遊びの環境
28.3 2歳児クラスの遊びの環境
1.1 乳児保育をめぐる現状
1.2 乳児保育の質の確保・向上のために
1.3 これからの乳児保育が目指すもの
第2章 乳児保育の歴史
2.1 乳児保育の始まり(明治~昭和初期)
2.2 乳児保育の基盤づくり(戦後~1980年代)
2.3 乳児保育の普遍化(1990年代~現在)
第3章 乳児保育における養護及び教育
3.1 養護と教育の一体的展開とは
3.2 3つの視点と5つの領域
第4章 子育て家庭を取り巻く社会的状況と課題
4.1 子育て家庭の変化
4.2 子育て家庭を取り巻く社会的状況と課題
第5章 諸外国における乳児保育
5.1 韓国の乳児保育
5.2 フィンランドの保育
第6章 保育所・認定こども園における乳児保育
6.1 保育所・認定こども園における乳児保育の概要
6.2 保育所・認定こども園における乳児保育の実際
第7章 乳児院における養育
7.1 乳児院とは
7.2 乳児院における職員の役割
7.3 担当養育制について ─アタッチメントを基本に─
7.4 育ちをつなげるために
7.5 保護者・家族支援、里親支援について
7.6 地域支援 ─家族と一緒に暮らし続けられるために─
第8章 小規模保育・事業所内保育における乳児保育
8.1 地域型保育事業の概要
8.2 小規模保育事業
8.3 事業所内保育事業
第9章 家庭的保育・居宅訪問型保育における乳児保育
9.1 家庭的保育事業とは
9.2 家庭的保育(保育ママ)とは
9.3 居宅訪問型保育とは
9.4 家庭的保育・居宅訪問型保育の遊びや生活の環境
9.5 家庭的保育・居宅訪問型保育の良さと課題
第10章 乳児保育における計画・記録・評価
10.1 保育の計画とは
10.2 乳児保育における指導計画
10.3 乳児保育における記録・評価
第11章 職員間の連携・協働
11.1 保育者間の連携・協働
11.2 多職種での連携・協働
11.3 職員間の対話
第12章 入園・進級時の配慮
12.1 入園時の子どもの様子と保育者の配慮
12.2 進級時の子どもの様子と保育者の配慮
12.3 3歳以上児の保育に移行する時期の保育
第13章 保護者との連携・協働
13.1 近年の保護者・家族支援
第14章 自治体や地域の関係機関等との連携・協働
14.1 自治体における子育て支援の取り組み
14.2 子どもを安心して生み育てるために
第15章 子どもと保育者の関係の重要性
15.1 「養護」において大切な関係性
15.2 「教育」において大切な関係性
第16章 6か月未満児の育ちと保育①
16.1 6か月未満児の発達の概観と配慮事項
第17章 6か月未満児の育ちと保育②
17.1 6か月未満児の基本的生活習慣と援助
第18章 6か月以上1歳未満の育ちと保育①
18.1 身体の発達
18.2 心と言葉の発達
第19章 6か月以上1歳未満の育ちと保育②
19.1 生活の流れ
19.2 排せつと着脱
19.3 遊び
第20章 1歳以上2歳未満児の育ちと保育①
20.1 1歳以上2歳未満の発育・発達の特徴
第21章 1歳以上2歳未満児の育ちと保育②
21.1 1歳以上2歳未満児の生活と遊び
第22章 2歳以上3歳未満児の育ちと保育①
22.1 「やりたい」や「こだわり」を受け入れる
22.2 信頼関係づくりと自発性・探索意欲の高まり
第23章 2歳以上3歳未満児の育ちと保育②
23.1 1日の流れと保育の環境
23.2 低年齢児の生活と遊びにおける援助の実際
第24章 乳児保育と食
24.1 乳児保育における食の援助
24.2 食事における配慮点
24.3 スプーンの持ち方の変化、遊びとのつながり
第25章 配慮が必要な子どもの保育①
25.1 1人ひとりの育ちを理解する
25.2 特に配慮が必要な“気になる子”の支援
第26章 配慮が必要な子どもの保育②
26.1 疾患のある子ども
26.2 医療的ケアが必要な子ども
26.3 医療的な配慮が必要な子どもを受け入れる際の配慮
第27章 乳児保育と環境①
27.1 保育の環境とは
27.2 0歳児クラスの生活の環境
27.3 1歳児クラスの生活の環境
27.4 2歳児クラスの生活の環境
第28章 乳児保育と環境②
28.1 0歳児クラスの遊びの環境
28.2 1歳児クラスの遊びの環境
28.3 2歳児クラスの遊びの環境